

|
特定非営利活動法人失敗学会 |
広告掲載について | 広告掲載について | 広告掲載について | 広告掲載について |
|
第22回失敗学会大阪夏の大会の報告【主催:失敗学会 大阪分科会】会場とzoomとのハイブリッド開催
【記録】 10:00 開会の挨拶 10:15 平松 雅伸(ひらまつ・まさのぶ)氏 11:30 昼休み 12:45 吉田裕(よしだ・ゆたか)氏 14:00 岡田敏明(おかだ・としあき)氏 15:00 休憩 15:15 福元満治(ふくもと・みつじ)氏 16:30 終了 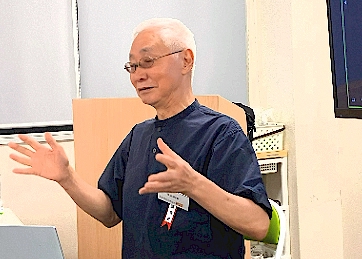 
概要(zoom の AI コンパニオンを元に)さらに、アフガニスタンでのNGO活動や水俣病、ハンセン病に関する問題が取り上げられ、 これらの経験から得られた教訓や支援活動の重要性が強調されました。会議全体を通じて、 歴史的な出来事や社会問題に対する正しい理解と、直接的な対話や支援の必要性が繰り返し指摘されました。 平松さん 太平洋戦争末期の特攻隊 平松氏が太平洋戦争末期の特攻隊に関する講演を行う。 彼は祖父の遺品である特攻隊員の懐中時計を中心に、 特攻隊の実態や出撃状況、地元の被害状況について詳細に説明する。 また、平松氏は自身の家族が経験した空襲被害についても語り、 戦争の悲惨さを伝える。講演では特攻隊員のデータベースや当時の 写真、資料なども紹介され、戦争の記憶を後世に伝える重要性が 強調される。 平松さん 太平洋戦争の規模と犠牲者 太平洋戦争に関する講演が行われ、戦争の規模、犠牲者数、 特攻隊の実態などが詳しく説明された。講演者は、戦争の悲惨さを 伝えることの重要性を強調し、自身の家族の経験も共有した。 質疑応答では、日本が太平洋戦争の教訓を十分に学んでいない のではないかという意見が出され、現代の日本社会や技術革新 との関連性についても議論された。 吉田先生 列車内閉鎖事故の影響 吉田さんは、列車内閉じ込め事故の事例と乗客への影響に ついて議論された。 2018年の大阪北部地震時の列車停止状況や、乗客の避難方法が 詳細に分析された。241列車が30分以上停車し、その約3分の2が 線路上での避難を余儀なくされたことが報告された。 また、避難開始までの時間や乗客の精神的負担についても言及され、 今後の対策の必要性が強調された。 吉田先生 列車閉じ込め事故の調査 吉田さんは続けて、大阪北部地震時の列車閉じ込め事故に関する 調査結果を報告された。乗客の不安やイライラ感は時間経過と ともに増加し、約1時間後には多くの乗客が降車を希望する ことが明らかになった。また、乗務員による乗客への協力要請が 社内の雰囲気改善に効果的であることが示された。 調査結果を踏まえ、異常時の乗務員対応マニュアルの改善が 提案された。 岡田先生 日本の製造業の海外移転 会議では、日本の製造業の海外移転による国内空洞化と、 その結果としての付加価値の喪失について議論されている。 岡田先生は、IT化やERPシステムの導入が必ずしも効果的でなく、 現場のプロセス改善や人材育成が重要であると指摘している。 また、日本の製造業が直面している課題として、技術や経験の 継承の問題、経営者の意思決定の重要性、そして現場を理解した ITシステムの必要性を強調されている。 岡田先生 日本の伝統的技術とngo 岡田氏は、失われた20年が30年に延長されたことについて講演し、 日本の産業における課題を指摘する。 福元さん アフガニスタンでの中村医師を中心とするNGO活動について報告し、 現地の状況や日本の伝統的農業土木技術を活用した 灌漑事業の成功例を紹介する。福元氏は、現地の文化や技術を 尊重することの重要性を強調し、西側諸国の近代化アプローチの 問題点を指摘する。次に、水俣病問題に触れ、地域での 啓発活動について言及する。 福元さん 水俣病に対する誤った認識 水俣病とハンセン病に関する誤った認識や差別の 問題が議論されました。水俣病はチッソの工場廃液に含まれたメチル水銀によって 引き起こされた食中毒であり、感染症ではないことが 強調されました。また、メディアや教育機関による情報の 伝達方法の問題点や、企業の責任、水俣病支援運動の特異性に ついても言及されました。会議では、これらの問題に対する 正しい理解と、直接的な対話の重要性が強調されました。 福元さん 水俣病とハンセン病 水俣病の経験と患者サポートの重要性についての 個人的な話から始まりました。議論は、ハンセン病の患者と その医師である中村哲の仕事に移り、ハンセン病の 歴史、文化的背景、そして患者への医療提供の課題についての 議論で締めくくられました。 福元さん アフガニスタン支援活動報告 アフガニスタンでの支援活動について詳細な報告が なされた。中村医師らのチームが、山岳部に診療所を設立し、 用水路を建設することで、砂漠化した地域を緑化し、農業を 復活させた取り組みが紹介された。また、現地の伝統的な自治システム「ジルガ」を活用し、地域住民との協力関係を 築いたことが強調された。支援活動は中村医師の死後も継続 されており、年間約4億円の予算で運営されている。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright©2002-2025 Association for the Study of Failure |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||