|
科学的な決定をするために
(文藝春秋『本の話』2004年4月号より)
畑村洋太郎(工学院大学教授)
京都・丹波での鶏インフルエンザ騒動を見ていて、恐ろしくなった。
私が「二八の原理」と呼んでいる経験則がある。組織にいる人間は二対八の割合で分かれるというものだ。
例えば、会社で「黙っていてもちゃんと仕事をする人」は二割しかいない。逆に、「サボる人、ダメな人、どうしようもない人」というのも二割いる。組み合わせると二対六対二の人口分布が成り立つ。
日本にあの規模の養鶏場が何軒あるかは知らないが、仮に千軒としたら、うち二百軒はダメな養鶏場ということになる。ということは、同じような養鶏業者がまだこの国には一九九軒もいるのか、そんなことを考えて恐ろしくなったのだ。
同時に虚しくもなった。
私は、数年前から「失敗学」という言葉を使い、講演や出版活動を通じて、多くの人たちにメッセージを発信してきた。古くはO157から、東海村臨界事故、地下鉄日比谷線脱線事故、雪印食中毒、明石市の陸橋での将棋倒し事故、外務省のプール金問題、BSE、SARS、宮城県北部地震、タンクやタイヤ工場火災、H2A打ち上げ失敗など、その時々の例を挙げて、文字通り「この国は失敗から学ばなければならないのだ」と主張し続けてきた。
これにはたくさんの人が共感してくれた。最近は、「やっと日本でも失敗に対する考え方・取り扱い方が変わってきた」という実感がある。それでもこういう事件は起き続ける。私の大声も隅々まではなかなか届かない。
しかし、救われる出来事もあった。
私は国交省のリコール原因調査分析委員会の委員長をやっているが、その調査研究のため先日、オートバイの製造工場に見学に行った。
失敗学の提唱者がお役人を連れてやってくるわけだから、向こうは嫌だろうなと思っていた。しかし、彼らは「どうぞ、どうぞ」と気持ちよく迎えてくれた。
実は一年前、その工場で講演をしたことがあって、三百人の関係者が私の話を聞いてくれたのだった。
工場長いわく、「先生には一年前の講演会できっちり教えてもらった。だからウェルカム」なのだという。見学では工場長が一緒にまわって説明をしてくれた。
そのとき工場の中に一辺八〇センチほどのダクトが張り巡らされているのが見えた。ダクト内部に溜まったゴミや埃は粉塵爆発の原因となるが、ダクトの中に入って掃除することなど、誰も考えもつかない。が、爆発の威力は凄まじく、炎がダクトを伝うので工場全体が瞬時に燃えてしまう。
私は化学の専門家ではない。これは昨年、タイヤ工場やコンビナートの火災が続発したとき、これらについて自分で考え、学んだ結果だ。それを私は新聞に書いたりした。
「ダクトってのは……」と私が工場長に話しかけると、「ちゃんと掃除してますよ、先生の新聞記事を読んでから」という。
よく見ると、ダクトが曲がっている部分には、掃除用の点検口がついている。
「掃除してみたら案の定、埃がたまってた。集めた埃を捨てないで燃してみたら、これがよく燃えたんです(笑)。
こりゃ大変だっていうんで、埃の溜まりやすい部分には点検口を付けた。ひとつ五万円かかりました。それでも工場が吹っ飛ぶよりはいい。もし掃除しないでこのままやっていたら、火災事故になっていたでしょうから」
嬉しい驚きだった。当たり前だが、日本の生産現場にもこういう人がいるのだと安心した。
日本も捨てたもんじゃない。自分の仕事を誇り、まじめに頑張っている人がたくさんいるのだ。
こういう職業意識の高い人と話していていつも感じることがある。
それは、「思考が科学的だ」ということだ。私は、こういう「科学的な思考」は、これからのリーダーに不可欠な条件だと思っている。
この『決定学の法則』は、まさにその「科学的な思考」を使って、様々な岐路で最善の決定をするための方法論を提案した本だ。
科学的な決定とは、簡単に言えば「事実に基づいて実証的に考え、決定することである。
本書では、決定の脈絡、迷い、躊躇といった脳内のメカニズムを分析し、その法則性を理解することで、「科学的な思考」の展開方法にアプローチしている。
多くの人はあまり「科学的な思考」をしない。その時の気分に左右されて、特に理由なく決めている。
かと思えば、プレッシャーのせいで難しくないことを過剰に恐れたり、考えれば考えるほど迷って決断できなかったり、逆によく考えなければいけないことを直感的に決めたりもする。
こういった非科学的な決定を続けていると、ここぞというときに真の「賭け」ができなくなる。
ビジネスからキャリアデザイン、ライフステージにおける決定まで、吉と出るか凶と出るか、結果がまるで読めないときがある。でも絶対にこの勝負には負けられない。そんなとき、思い切って賭けなければいけないが、サイコロを投げるような当てずっぽうなやり方ではいけない。科学的に思考し、決定し、賭けるのだ。
「自己責任」という言葉を安易に使う風潮には感心しないが、現在の日本人は、自分で考え、決定しなければいけない時に立たされている。
そんな時代を生き抜くためにも多くの人が本書で"自分自身の決定学"を手に入れてほしいと思う。(『決定学の法則』畑村洋太郎著・三月下旬発売)
|
| |
|
|
|
2033年12月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 失敗知識DB |
 |
|
失敗年鑑
|
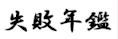
|
|
個人会員紹介
|
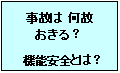
|
|
法人会員紹介
|
 |
|
失敗体験施設名鑑
|

|
|

