| プログラム |
| 日付 | 講師 | 内容 |
第1回
4月20日(土)
(10:40-12:10) | 佐伯 徹
 | 失敗学概論~ミニ事例解説
-失敗学ってどういうもの?-
2018年M1場外騒動を考える |
(失敗学概論)
失敗学とは?失敗とミスは違います!失敗の本質を理解し『後世へ継ぐ』ことの大切さや、失敗学会データベースの活用方法について紹介します。
(ミニ失敗事例解説 )
2018年12月2日:M-1グランプリ事務局により開催している「M-1グランプリ」が開催された。開催終了後、インスタグラムのライブ配信機能を利用して審査員を批判。その結果、多くのメディアを巻き込んだ論争となった。その報道の経緯を踏まえ検証していく。 |
第2回
5月11日(土)
(10:40-12:10) | 大澤 勲
 | 「電気仕掛け製品」の失敗や事故はなぜ起こる?
-破壊・発熱を机上実験しながら事故失敗例を説明- |
| 現代社会は身の回りが「電気仕掛けの製品」で埋もれています。家電など何気なく使っていますが、製品には使用荷重、使用電圧、使用温度、使用時間…などの限度が明記されています。それを超えると危険です。その理由は内部で使われている部品・材料に「定格○○(例:定格電圧)」があり、「定格」を超えると破壊・爆発・火災・発熱等が起こります。机上実験で示しながら産業設備や家電製品の失敗事例を説明します。 |
第3回
6月15日(土)
(10:40-12:10) | 岩崎 雅明
 | 使用済み核燃料の話
-10万年の安全を確保するために- |
| 原子力発電で発生した使用済み核燃料は、高い放射能を長期間出し続けることから、その最終処分をどのようにするか、未だ国として結論が出ていません。今回は、危険な(強い放射能を長期間発する)成分は何か、地層処分(地中深く埋める)がベストの方法と言われるが、それは何故なのか、諸外国はどのように取り組んでいるのか、そして、10万年の安全を確保するために、どうしたら良いか、などについて説明します。 |
第4回
7月13日(土)
(10:40-12:10) | 佐々 正光
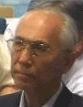 | 近江商人の経営理念「三方よし」や、新渡戸稲造の「武士道」などは失われてしまったのか?(儲かれば何をしても良いのか?) コンピュータ社会では、どうなるのか?
-過去の問題点(失敗事例など)を参考に、現在の問題点を探る- |
- コンピュータ社会における個人や、社会の公共性・経営理念と、「便利と不便」、「安全と危険」を、どのように選択すればよいのかを検証する。
- 依然として横行する詐欺犯罪に、対抗する方式はあるのか?
- 自動車だけでなく、飛行機、ドローンなどの飲酒運転や“ながらスマホ”などの危険性を理解させ、撲滅するためにはどうすればよいのか? 特に、今後ますます増加する外国人に対し、外国人と日本人との文化の違いを、どのように認識させればよいのか?
|
第5回
8月31日(土)
(10:40-12:10) | 平松 雅伸
 | 東日本大震災~大川小学校の悲劇・釜石の奇跡から学ぶもの
-南海トラフ大地震津波を前に、減災につながる防災教育を考える- |
- 2011年3月11日、東日本大震災の津波で、逃げ遅れた大勢の方が犠牲となった。
- 学校の避難では、釜石市の子供たちは、日頃の防災教育訓練の通り、率先避難者として、保育所の幼児の手を引き、街の人たちと避難し、津波の状況で、更に高地へ避難し、一人の犠牲者も出さなかった。
- 大川小学校では、運動場で待機し、すぐ隣には授業でも行ったことのある裏山に避難することなく、先生と小学生の殆どが犠牲となった。 調査委員会でも深層原因は明らかにされなかった。
- 2つの事例を対比し、津波避難の在り方~防災教育の基本を考え、西日本で襲来する南海地震津波からの避難を考えたい。
|
第6回
9月14日(土)
(10:40-12:10) | 三国 外喜男
 | イベント・プロジェクトなどのグループ作業は何故うまくいかないかを、失敗学で考える
-朝令暮改は成功かも- |
プロジェクトの成功を祈って頑張ろーと拳を突き上げるけれど、どれだけのメンバーがその気になっているのでしょうか。お付き合いで取りあえずガンバローと・・・
失敗は物事を否定するところから始まります。部下に声を上げて叱り飛ばしたいところですが、近頃では無理をするとパワハラの文字が頭をよぎってきます。この講座でリーダーもスタッフも成功のコツを学んでみませんか。 |

